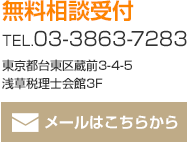現在コロナ禍で飲食業は売上の激減に為すすべが無いようですが、少し視点を変えてみましょう。
飲食店の売り上げに影響する要素は、主だったもので下記の通りでしょう。
1.立地 2.単価 3.味
付け加えれば、4.店の雰囲気 5.接客態度等でしょう。
もう一つ重要な要素があります。
私、税理士のモットーは、「お客様にとって最も重要なことは、何をしてくれたかではなくてどの様な気持ちにさせてくれたか」です。
「心の波動」は不思議とお客様に伝わります。どんなに繕っても「心の波動」はストレートに伝わります。
「味の余韻」と共に、「気の余韻」もリピーターを増やすためには、重要な要素です。
2020/08/23新着情報
中小企業庁は、令和2年度第一次補正予算経営資源引継ぎ補助金の公募(7月13日~8月22日)を実施しています。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される中小企業に対して事業再編・事業統合等に係る費用の一部を補助することで、経営資源引継ぎの促進・実現を支援する補助金です。
*経営資源引継ぎに係る経費の一部を対象に交付される補助金です。
(対象となる経費)謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料で、補助対象経費の
2/3で、支給額に上限があります。補助金の交付は令和3年3月下旬
です。
2020/08/11新着情報
令和2年4月20日に新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置が閣議決定されました。
1)納税を猶予する「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった納税者は、1年間国税の納付を猶予することができます。
担保の提供は不要で、延滞税もかかりません。
主な条件としては、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していることで、一時に納税が困難であることです。
2)新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の繰り戻しによる法人税税額の還付を受けられる場合があります。
災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることが出来る制度です。
2020/08/02新着情報
表題の歌は、昭和21年にリリースされた歌謡曲で、京都府舞鶴港が舞台となっています。
私の父は、戦後旧ソ連邦のシベリアに抑留され、約2年後に帰還船で舞鶴港に到着しました。「皆様本当にご苦労様でした。この船は日本行きです。」という船内放送の後、この歌が流れたそうです。歓喜と安堵の声が挙がったことでしょう。
最近「You Tube」でこの歌を聴く度に、父への追慕の念が高まり、舞鶴港を訪れたいと強く思っていました。移動自粛が解除された後の日曜日(6月21日)に日帰りの日程を組みました。
入り江の奥にある舞鶴港を見下ろす丘の上に立つ「舞鶴引揚記念館」には多数の当時の資料とともに、父が抑留されていた「収容所」の内部がリアルに再現されており、父の話していた内容と一致していました。
望郷の念に駆られ日本への帰還を強く願う病床の戦友に対して、為すすべもなくその最期を看取ったと話す父の顔が浮かんできました。日本へ帰還した翌年に私は生まれたようです。
記念館で配布している舞鶴入港の引揚船一覧表を見て、いつ、どの船で父が帰還したのか知りたくなり、引揚者名簿等(旧軍人・シベリア抑留体験者)の照会先である厚生労働省 社会援護局へ「ロシア連邦政府から提供された旧ソ連邦抑留者個人資料の開示申請書」を送付しました。申請書の注意書きには、「調査の結果、該当する資料が無い場合があります」「提供する資料は、ご本人の漢字氏名以外はロシア語で書かれています」とあり、送付しても父が乗船した引揚船名を知ることが出来ないかもしれないとも考えましたが、本人確認等の書類を添付して送付しました。
記念館を出てJR東舞鶴駅に向かう途中に、菊池章子・二葉百合子の「岸壁の母」の舞台である桟橋をタクシーの車窓から見ました。この歌も時々聴いていましたので、胸に迫るものがありました。
2020/07/24新着情報
2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言書の保管が出来るようになりました。
(法務局で遺言書を保管するメリット)
①紛失や保管場所を忘れる心配がない
②破棄・改鼠・隠匿されない
③家庭裁判所での検認が不要
*申請先は法務局で、文面をチェックされるため封をせずに提出する。検認が免除されることから様式不備も指摘してくれます。
*自筆証書遺言書の保管を申請できるのは、遺言者のみです。
*保管手数料は、3,900円です。
*遺言者が死亡するまで遺言者以外の者は閲覧できませんが、遺言があることの確認は遺言書保管事実証明書の交付請求によって行います。
2020/07/14新着情報
個人の相続においては、個人の相続人が一般的ですが、法人格を有する者が遺贈を受ける場合があります。
(1)受遺者が代表者の定めのある人格なき社団や管理者の定めのある財団である場合
その社団を個人とみなして相続税が課税されます。
(2)受遺者が株式会社である場合
株式会社が遺贈により取得した財産が譲渡所得に基因となる資産の場合には、被相続人が法人へ時価で譲渡したものとみなされます。法人が遺贈により取得した財産の価額は各事業年度の所得の計算上益金の額に算入されます。
また、株式会社が遺贈により財産を取得したことによって、その法人の株式の価額が増加することになりますので、株主に対して被相続人から遺贈があったとみなされます。
従って、受遺者が株式会社の場合には、譲渡所得、法人所得、相続税が発生することになります。ややこしいので、税理士にご相談下さい。
2020/07/04新着情報
(1)法人が取得し、法人名義である場合
償還又は譲渡のいずれも取引仕訳により差額が特別損益(評価損を含む)に計上される。
(2)個人が取得し、個人名義である場合
償還を受けるという行為は、優先的施設利用権を自ら放棄して、単に貸付債権を回収する行為であり、ゴルフ会員権を譲渡したことにはならず、譲渡所得の起因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の資産の譲渡による譲渡所得と通算できない。
また、これにより償還不足額が生じてもその償還不足額は「家事上の損失」として所得税の計算上考慮されない。
なお、個人が平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は他の所得と損益通算できない。
2020/06/20新着情報
「経営者保ガイドライン」は2013年に全国銀行協会と日本商工会議所が策定した融資債務に対する個人保証の指針ですが、昨年12月に特例を定め、新旧の経営者に融資債務に対する個人保証を求めることを原則禁止することにしました。
この特例を設けたのは、新旧の経営者に個人保証を求めると、後継者の円滑な事業承継を妨げるケースが認識されるようになったことがその背景にあります。2020年4月から適用されますが、強制力は持ちません。
昨今の実情としては、直系の親族が事業を継承することが困難になり、従業員等の第三者に後継を求めるケースが多くなりつつあります。したがって、個人保証をすることにかなりの抵抗感がでてきています。
「債権保全」のみを従来通り踏襲しようとする金融機関等の債権者側が「事業再生」の観点を強く認識することが必要な時代背景となってきているようです。
2020/06/10新着情報
自筆遺言には誤りが多い為、公証人役場で作成してもらうことになりますが、人生で何回も作成することになる人は殆どいないでしょう。
公正証書遺言の文案の準備ができたら、本人と一緒に決められた日時に公証人役場へ赴くことになります。高齢の者がほとんどでしょうが、実際の手続きの場に本来は付き添いの相続人や利害関係者は立ち会えないことになっています。
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人から聞き知った事柄をその場で書面にし、本人に読み聞かせることになっています。実務的には、本人が公証人役場に出向いた際には、既に書面は完成しているのですが、それを本人と証人2人が相違ないことを確認し、署名・押印することになります。署名・押印は原本だけになされますが、ほかに正本と謄本の二部が本人に返却されます。
2020/06/01新着情報
新型コロナウイルスの問題で本年4月に入り大手企業では売り上げが大きく落ち込み、コミットラインを設定し、手元資金を確保する動きが出ている。
コミットラインとは、一定期間にわたって貸し出し限度額を設定し、極度額の範囲であれば何度でも資金の借入・返済が出来る融資枠のことで、融資を行うことを約束(コミット)する契約のことである。その対価は有償で、コミットメントフィーと呼ばれ、もちろん金利も発生する。コミットフィーは、枠の設定料という名目であるが、元本が存在しないことから、利息制限法・出資法違反ではないかという議論もあったが、特定融資枠契約に関する法律が制定され、利息制限法・出資法の特例である旨規定された。
また、即座に融資するため財務状況の制限(自己資本比率)等の条件が課せられる。
2020/05/23新着情報