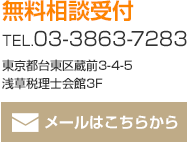標題の問いかけは、あるメンタル系の書籍の中にあった文章です。
約2年近く抑圧された世界に閉じ込められたとの感慨が湧いてくるのは、私だけではないでしょう。
しかし、コロナに振り回された時間を眺めてみると、自分自身に起こった小さな変化があることに気付きました。
以下に、箇条書きにしてみます。
①出かける時間がかなり減少したため読書量が増加しました。
②高齢者の範囲に入るため、重症化や死亡リスクが増加するとのことで「もしもの時」への対応で身辺整理いわゆる断捨離をしました。
③過ぎ去りし日々を十分に回顧する時間が増えたため、自分自身を十分に分析して識ったような気がしました。
以上の小さな変化が生じた結果、「死」から現在を眺めるようになりました。
この書籍には、次の文章もありました。
【これからの新しい時代を生き抜いていくため、古い自分から脱皮し、変化を遂げる必要があります。そのために、一度、死を覚悟するくらい苦しい精神状態まで追い詰められる必要があります。いわば、新しく生まれ変わるための試練です。潜在意識は、それを与えるために、新型コロナウイルス騒動があったのです。】
2021/09/18新着情報
配偶者の税額軽減制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、Ⅰ億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税が課税されない制度です。
適用すれば税額を大幅に軽減することが出来ますが、残された配偶者の年齢次第では、二次相続を見据えた検討が必要となります。
(不動産に関しての留意点)
賃貸不動産は配偶者以外の相続人が取得することが有利であるようです。 賃貸用不動産で一定の要件に該当するものは、小規模宅地等の減額特例の適用ができます。
賃貸用不動産を配偶者が相続した場合には、相続後に発生する収益により二次相続における配偶者の相続財産を増加させる可能性があります。
ただし、配偶者の生活資金の原資となる場合には、配偶者が相続することも選択肢となります。
一次相続以後の相続人の事情の変化もありますので、あらゆる場合を想定して、分割することが重要となります・
2021/08/23新着情報
クライアントにブックカフェがあります。
1906年に就役した英国の戦艦の名前を店名にしています。オーナーは戦記物や戦艦・戦闘機等の個人の蔵書を提供しています。
戦記や戦艦に関する作家の講演会を開催しており、ファンが多数集まるカフェになっております。また、城郭ファンも集まり出したとのことで、私が所蔵している城郭や城下町に関する書籍をファンのために陳列させて頂くことになりました。城郭等のファンは、興味の対象が個々人で細分化されているため、仲間と行動することはあまりしないのですが、同好者と情報交換もしたいと思う様になりました。
このカフェは、江東区平野に在ります。
2021/07/13所長ブログ・新着情報
特定役員退職金(勤続年数が5年以下の役員等が受ける退職金)は平成24年の改正により退職控除が行われた後の支給額に対して2分に1を乗じる計算が出来なくなりました。
ただし、勤続年数が5年以下で特定役員退職金等に該当しないもの(短期退職所得等)に係る退職所得の金額の計算につき、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1課税措置が廃止されます。
この改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。
勤続年数が5年以下の従業員でこのような多額の退職金を受給する例は、中小企業には無いとみられます。
2021/06/06新着情報
平成29年1月の最高裁の判決です。
従来の養子縁組に対する実務の考え方を後押しする判断を後押しする判断といわれている。
実子がいても養子は一人までで、実子がいなければ二人まで相続人に含められる。節税目的であっても当事者の意思が確認されれば養子縁組は無効とされることはなくなった。
ただ、相続税法は「相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合は、税務署長の判断で養子を算入せずに税額を計算することが出来る」と定めている。すなわち、いかなる場合も認められるという訳ではない。
2021/04/28新着情報
退職金(退職一時金)の分割払いについてはその未払金部分を含めて一括して損金の額に算入できますが、退職年金は、その支給時期において損金の額に算入されます。従って退職時に計算される年金総額を未払金等に計上してもその未払金等の額を損金の額に算入することはできないことになります。
退職一時金を支払う財源が無い,若しくは不足する場合に、その支給額を分割払いした場合に退職年金の支給であると判定される恐れが無いとは断定できません。
法人税法上、退職一時金の場合、どの程度の期間にわたって分割することが出来るかは明らかではありません。
既に、数年間にわたり分割払いされている場合に退職一時金の形態ではないと言い切れる根拠はあるでしょうか?問題提起としてこのブログを掲載しました。
(法人税基本通達を一部引用)
2021/03/29新着情報
贈与税は、相続税の保管税という性格から、その納税義務者である受遺者は、原則として個人に限るとともに贈与税も個人に限られます。
従って、相続(自然人の死亡)という事実が起りえない法人については、相続税の補完税としての贈与税の役割が生じませんので、法人から贈与により取得した財産については、贈与税を非課税とし所得税(一時所得)を課することとしています。
2021/02/21新着情報
私がいわゆる「断酒」をしたのは平成19年(2007年)3月1日ですので、約14年前になります。毎日浴びるように飲んでおりましたので、行きつけの飲み屋さんからは、断酒したのではなく、違う店に変えたのだと思われていたようです。
全く飲まなくなったらしいと知れてからは、賞賛の言葉や誤解の言葉が降ってきました。
飲酒をやめる直前の検査では、内臓疾患等は無かったのですが、脚気の疑いがあり、また何故か大腿部の痙攣が酷く、耐えられない状態でした。断酒会や病院での断酒治療は受けませんでした。
特別なことは何もしていないのですが、強いて言えば「深層心理・潜在意識」に働きかけたということでしょうか。
心理学等にはもちろん疎いのですが、簡単な日記を毎日つけ、飲まなくて良かったとの想いを噛みしめるようにしました。飲酒の楽しさは思い浮かべず「飲むのが怖い」「飲んだ後が地獄」とのイメージを深層心理に強く植え付けたことになるかも知れません。
決して「意志の力」ではなく「恐怖心」を鮮明にしそれを潜在意識に訴えたことになるのでしょう。
すべての方々に当てはまるとは思われませんが参考になれば幸いです。
2021/01/26新着情報
「連れ子」で再婚する場合の注意点
連れ子の親が再婚相手より先に亡くなっている場合で、次に再婚相手が死亡したときには、連れ子と再婚相手が養子縁組をしていないケースでは、連れ子は相続人に該当しないため、悲劇と言ってもよい状態に置かれることがあります。自分の親の再婚相手がなくなるまで面倒を見ても、遺言に遺贈の文言が無ければ相続人ではないため、その苦労は報われなくなります。
自分の親が亡くなった時、自分の親の再婚相手から言い出さない限り、養子縁組に進めないでしょうね。
このケースで相談を受ける場合には、何ともやるせない思いがします。
2020/12/26新着情報
*スタートアップ・・・比較的新しいビジネスで急成長し、市場開拓フェーズある企業や事業
*ディープ・ラーニング・・・人間の神経回路を模した情報処理システムを構築し、コンピューターが自らデータを認識して学んでいくこと
*スレレオタイプ・・・固定観念や偏見・差別などの類型紋切型の観念
*ダイバーシティ・・・多様な人材を積極的に活用しようとする考え方
*パラダイムシフト・・・その時代や分野において、当然のことと考えられていた認識等が 劇的に変化すること
*ヘリコプターマネー・・・中央銀行・政府が国債買い入れで大量の貨幣を市中に供給する経済政策
2020/11/28新着情報