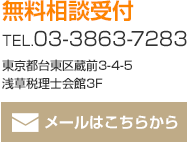マレーシア・クアラルンプールの日本人会への個人会員としての入会は、マレーシア入国管理局の長期滞在許可証(ビザ)の取得が前提条件となります。このビザの取得に4か月も掛かりましたので、仮会員証を受領した時は、ホッとしました。入会費用は、入会金200リンギット(以下RM)、保証金550RM、月額会費70RM(1年分の840RM)の合計額1,652.40RMで日本円に換算(1RM約25円)すると約41,310円でした。
日本人会の建物は、クアラルンプールのミッド・バレー地区の小高い、森に覆われた丘の上にあります。日本人幼稚園やマレーシア人のための日本語学校が併設され、図書館(約6万冊所蔵)、マーケット、レストラン、カフェ各種エージェントの事務所等があり、ゲートの警備も厳重です。仮会員証が発行されるまでは、入館する際にはパスポートNO、携帯電話番号、詳しい用件内容のチェックがあり、不審者として警戒している態度でした。
この建物の中は広くて迷う程です。キッチンルーム・ダンスホール・剣道場・柔道場・音楽室等があり、会員のための趣味・講座が約80もあるそうです。
私は、男性合唱団のグリークラブに入団しました。次回に詳しくお話しします。
2016/11/06新着情報
時系列でスケジュールを示しますと・・・
10月3日 23:45 羽田発
10月4日 06:10 クアラルンプール着
09:30 ブキッ・ビンタンにある外資系銀行前にてビザ申請サポート会社の通訳と待ち合せ、華僑
系銀行スタッフと保証金相当の定期預金と利息受け口の口座開設手続きを行う。
MM2Hビザの認可のためには、保証金が必要なためです。
11:10 近くの病院にて健康診断を受け、血圧がやや高めでしたが、パスしました。
10月5日 15:00 ビザ認証済み証が貼付されたパスポートを受け取る。
16:00 現地の弁護士に依頼して、遺言書(マレーシアで遺言書がないと直ぐに解約できない。)
と委任状を作成した。
保証金相当の定期預金(1年)の金利は年2,9%で、ゼロ金利で騒がれている日本からみれば、破格の高金利です。
2016/10/13所長ブログ・新着情報
本年5月上旬に申請したMM2Hビザの承認がやっと下りました。通常は2~3ヵ月で承認許可がされるようですが7月5日にラマダンが開始されたため4カ月かかったようです。
これで終わりではありません。ビザの本申請のために本人が現地に行かなければなりません。現地に行く前に保証金らしいのですが、マレーシアの指定銀行に口座開設をする準備として指定金額を送金します。そのあと現地で本人が指定された銀行で口座開設をすることになりますが、代行申請代理店の通訳が同行しますので、英語が不得手でも構いません。また、同日に健康診断を指定された病院で受けます。翌日MM2Hビザの添付されたパスポートと定期預金証書を受け取れば完了です。
10月上旬に本申請に行きますので、帰国後に所長ブログで状況を掲載します。
2016/09/11所長ブログ・新着情報
本年4月に公表された「小規模企業白書」による廃業に関する分析結果では、2012年から2014年までの二年間に廃業した20人以下(卸・小売業、サービス業は5人以下)の小規模企業者は年平均で約23万件でした。
廃業理由で最も多いのは「病気・高齢」で40%、次いで「事業不振・先行き不安」の12%でした。日本の小規模企業者は2014年で企業総数の85%で、そのうち6割は個人事業者で、そのその半数あまりは常用雇用者がゼロでした。
また、小規模企業が営む事業所数も2014年には108万減少しました。このうち、約100万は飲食業を含む小売業の減少分です。
若い経営者の積極的な海外展開に大いなる期待が寄せられています。
2016/08/22新着情報
受益権の複層化とは、受益権を元本受益権と収益受益権に分けることです。
不動産の場合、不動産そのもの(元本受益権)と家賃収入(収益受益権)に置き換えることが出来ます。
複層化における受益権の評価(財産評価基本通達202)では、以下のように規定されています。
収益受託者が取得する収益受益権の評価額・・・課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき
利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの
期間に応ずる基準年利率による複利原価率を乗じて計算した
金額の合計額
元本受益者が取得する元本受益権の評価額・・・財産評価基本通達に定めるところにより評価した課税時期に
おける信託財産の価額から、収益受益権の評価額を控除した
価額
従って、受益権が複層化された信託の信託財産が、高収益資産の場合には、元本受益権の評価は低くなります。つまり、評価の低い元本受益権を信託設定時に、相続人予定者に生前贈与しておけば、相続税対策になるという考え方もありますが、受益権が複層化された信託が、信託財産の全部の評価とされるとする説もあります。
2016/07/27所長ブログ・新着情報
法人格とは、法律の規定により権利能力(人格)が付与された団体及び法人であり法人の権利能力(人格)が法人格です。
法人格の種類としては、株式会社、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団・財団法人が
あります。
このうち、合同会社が株式会社より安価で設立することが出来るため、新設法人では、この法人格を選択するケースが最近目立っていますので、その特徴を説明します。
設立のための費用が、株式会社の約3分の1で、設立時に定款認証は不要です。株主総会の代わりに社員総会があり、業務執行する役員は業務執行社員とされ、原則として任期の定めはありません。
2016/07/12新着情報
本年4月1日から未成年者向けの少額投資非課税制度(ジュニアNISA)が始まりました。
ジュニアNISAは年80万円まで親が未成年に代わり株式や投資信託に投資すると、配当や売却益に本来かかる20%の税金が5年間かからない制度です。
ジュニアNISAの現在の口座数が伸びていないのは、引き出し時期に制限があり、口座開設手続きもやや面倒なためと言われています。
成人向けはいつでも引き出し可能ですが、ジュニア向けは子が18歳になるまで、売却しても原則、引き出せません。
また、口座開設に必要な書類も少なくなく、親子それぞれの本人確認書類に加え、親子関係を証明する書類も必要となります。
口座の名義人は子供本人ですが、資金は祖父母や両親が出して運用・管理します。19歳まで利用できますが、資金の引き出しは18歳になるまでできません。大学への進学資金や結婚、住宅取得としての活用が想定されています。
子供が小さいころから利用すれば計画的に将来の教育資金が貯められます。また、祖父母が孫のために贈与をする場合の受け皿としても利用できます。
2016/06/27新着情報
「私募債」とは、簡単に発行できる社債の一種です。
主に取引先の経営者や知人に、発行した社債(私募債)を買ってもらうことにより、資金を調達しようとするものです。
(私募債が発行できる条件)
1.法人であること。
2.社債を購入する人が50名未満であること。
3.社債一口の金額が、社債発行総額の50分の1よりも大きいこと。
社債の譲渡制限を設けること。
以上の条件をすべて満たした少人数私募債であれば、自社内での手続きのみで発行することができます。
(メリット)
1.返済計画に余裕が持てる。
2.比較的簡単に発行できる。
3.協力が得やすい。
4.社債の管理会社は不要。
(デメリット)
1.募集は縁故者に行うことが原則なため、必要な資金が調達できない場合がある。
2.担保や保証人がいないため、信用面のリスクが高く、引受人が見つけにくい場合がある。
2016/06/20所長ブログ・新着情報
マネーロンダリングとは、犯罪などで得た汚れた資金を、その出所を偽装したり隠したりしてきれいな資金に見せる(資金洗浄)行為を言います。
わが国では、平成12年に「組織犯罪処罰法」が制定され、届出の対象が従来の薬物販売収益に係る取引から200を超える重大犯罪収益に係る取引に拡大され、平成19年には「犯罪収益移転防止法」が制定され、届出対象事業者が従来の金融機関等からクレジットカード事業者等に拡大され、平成22年には為替取引を行う資金移転業者が届出義務のある特定業者に追加されました。
届け出られた疑わしき取引に関する情報は国家公安委員会・警察庁で管理され、必要に応じ検察官・司法警察職員・税関職員等の捜査機関に提供されています。
最近の事例では、米国などでだまし取られた約3億円を日本国内の口座から不正にひきだしたとして、ナイジェリア人と日本人の9人が組織犯罪処罰法と詐欺の疑いで逮捕されました。(6月11日の報道)
2016/06/16所長ブログ・新着情報
Dept Equity Swapとは、債務(Dept)と資本(Equity)を交換(Swap)することです。
債権者から見たときは、「債権の株式化」であり、債務者から見たときは「債務の資本化」ということです。
つまり、債務者である会社は、借入金を返済しなくてもよいかわりに、債権者に株式を発行し、他方、債権者は貸付金を回収しないかわりに債務者に対する資本金を債権額と同額増資することになります。
会社に社長借入金がある場合、社長の相続の時に会社に対する貸付金も相続財産になります。業績が悪く、返済の見込みがない貸付金に相続税がかかることになりますので、相続人はその貸付金を相続財産にすることを避けたいと思った場合にこの取引を利用します。
会社に多額の繰越欠損金が社長借入金以上にある場合には、社長がその貸付金を会社の贈与することにより、デット・エクイティ・スワップと同様の結果を得ることが出来ます。
2016/06/12新着情報